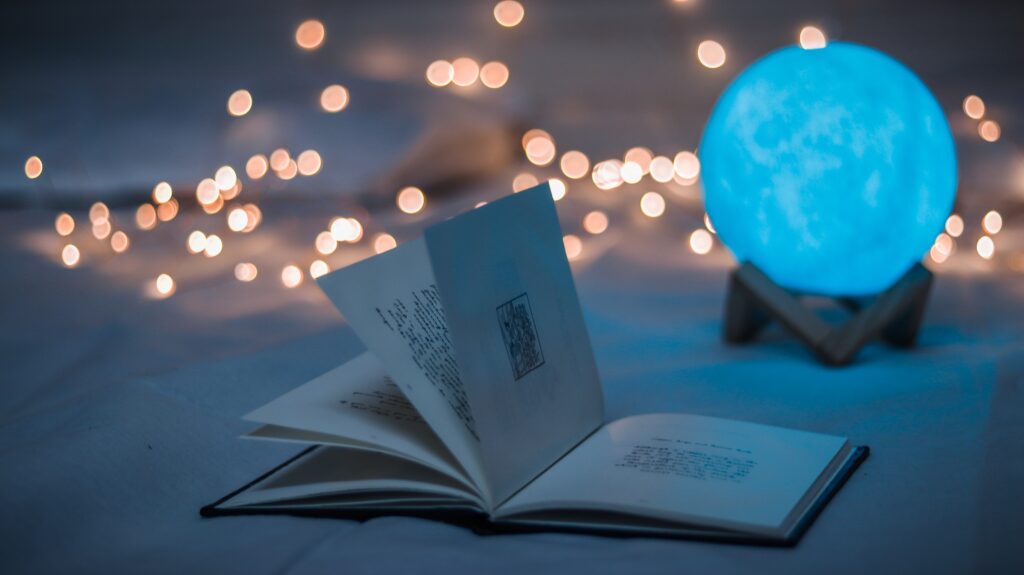

本記事ではこのような悩みを解決していきます。
✔本記事を読んで分かること
①「オーディオブック」と「電子書籍」と「紙の本」のそれぞれの特徴
②それぞれの場面に適した使い分け方法
最近は色々な媒体で読書をできるようになりましたが、「結局どれを使えばいいの?」と悩むことが多くなりましたよね。
今回はそんな悩みを抱える方へ向けて「オーディオブック」「電子書籍」「紙の本」それぞれの特徴をまとめていきたいと思います。
これからオーディオブックを始めてみようかな?電子書籍を使ってみようかな?と考えている方の参考になれば幸いです。
それぞれの特徴まとめ
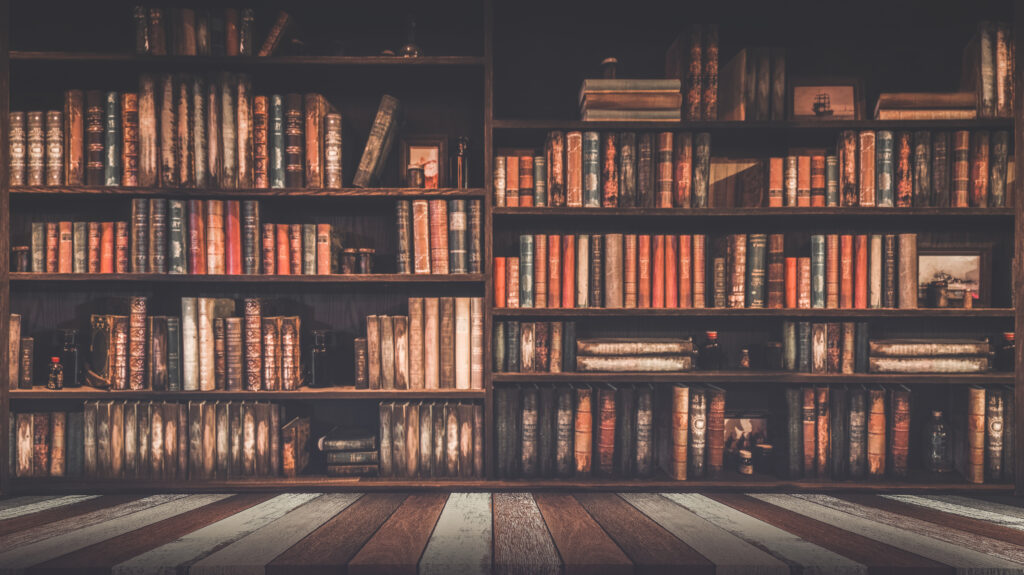
それぞれの特徴を表にまとめました。それぞれ長所と短所がありますね。
| 比較項目 | オーディオブック | 電子書籍 | 紙の本 |
| ①価格 | △ | ◎ | ○ |
| ②持ち運びやすさ | ◎ | ◎ | △ |
| ③書籍の数 | △ | ○ | ◎ |
| ④本の置き場所 | ◎ | ◎ | × |
| ⑤読みやすさ | △ | ○ | ◎ |
| ⑥機能性 | ○ | ◎ | △ |
| ⑦暗所での読書 | ◎ | ○ | × |
| ⑧保存期間 | ◎ | ◎ | △ |
| ⑨読書量の確保 | ◎ | ○ | △ |
| ⑩バッテリー | △ | △ | ◎ |
1つずつ解説していきます。
①価格

価格については、「電子書籍」と「紙の本」に軍配が上がります。
電子書籍は定期的にセールなどがあり、半額で購入することができます。また、紙の本は中古品などを求めればかなり安く購入することができますね。(「中古で本は購入しない」という方もいると思うので、ここでは紙の本の評価は「○」にしています。)
一方、オーディオブックはこれらよりも少し割高です。おおよそ1冊あたり2,000円~3,000程度します。
価格だけで見ると、「電子書籍」「紙の本」が強いですね。
また、紙の本はメルカリやBOOK・OFFといったところで売ることができます。
新作を新品で購入し、読んだ後すぐに売却すれば実質格安で読書できたも同然なので、その点でも紙の本は強いですね。
②持ち運びやすさ
持ち運びやすさは「オーディオブック」と「電子書籍」が良いですね。
オーディオブックや電子書籍はスマホ1つあれば読書ができますが、紙の本は持ち歩かなければなりません。
また、複数のデバイスで連携ができるので、外にいるときは「スマホ」、家にいるときは「タブレット」で読書といった使い方ができるのも良いポイントですね。
③書籍の数
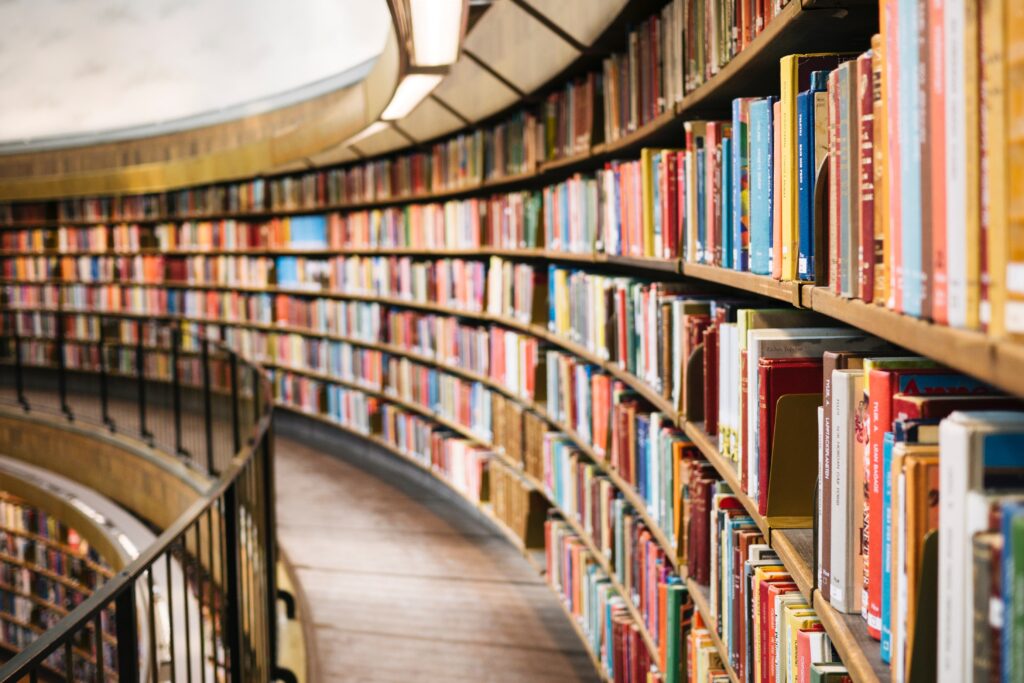
書籍の数についてはダントツで「紙の本」です。もう最強です。
オーディオブックや電子書籍にはまだ対応していない本も多くあります。「この本読みたい!」と思った本が見つからないこともしばしばあります。
また、「図が多い本」など紙で読んだ方が良い本というものもあります。
④本の置き場所
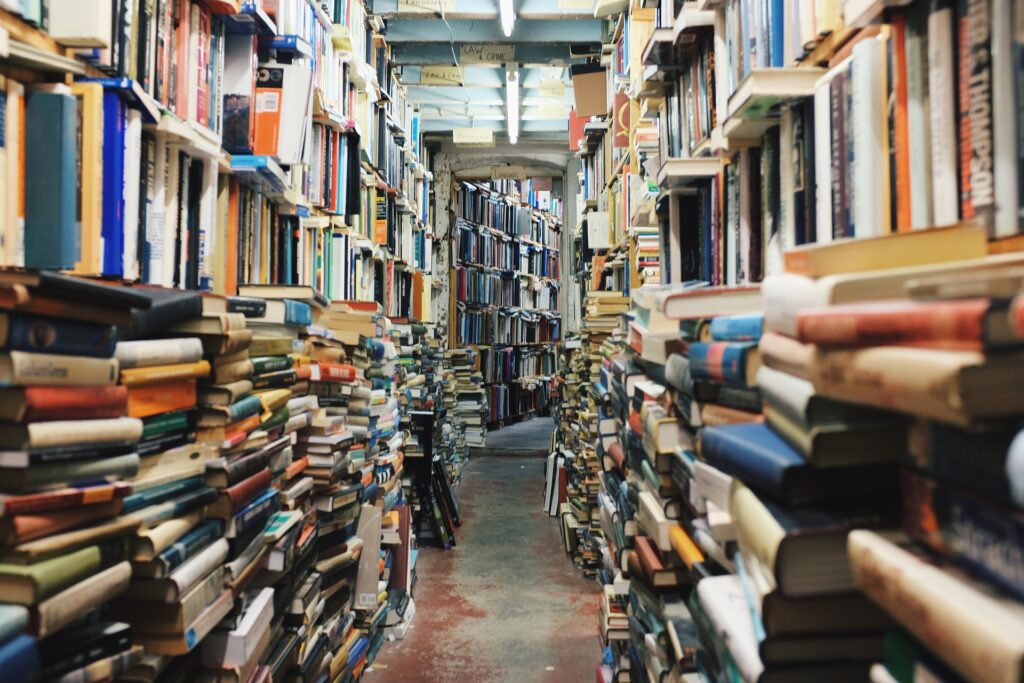
本の置き場所は「オーディオブック」と「電子書籍」が勝ちですね。
何と言っても「場所を取らない!」この強みは大きいですね。
紙の本はどうしても部屋を圧迫してしまいますが、オーディオブックや電子書籍はデバイスに1つに収まるので、部屋を広く使えます。
引っ越しの時なども本がない分楽に進むんですよね。
⑤読みやすさ

読みやすさは「紙の本」が一番良いですね。
なんといっても、紙の本にはペラペラめくりながら斜め読みができるという強みがあります。
次点で「電子書籍」、最下位は「オーディオブック」です。
オーディオブックは斜め読みができません。この点はどうしてもネックになりますよね。
⑥機能性
機能性とはここでは「メモ機能、検索機能、マーカー機能」といった機能をまとめて定義します。
機能性で言うと「電子書籍」に軍配が上がります。
電子書籍は、気になる部分に簡単にマーカーを引くことができますし、後でマーカー箇所をまとめて確認することもできます。
わからない単語はその場ですぐに意味を検索することもできるので、本当に読書しやすいんですよね。
「オーディオブック」にもメモ機能に近い機能はあり、気になった箇所を保存しておき、後で聴くことができます。
こういった機能は紙の本にはありませんよね。
⑦暗所での読書
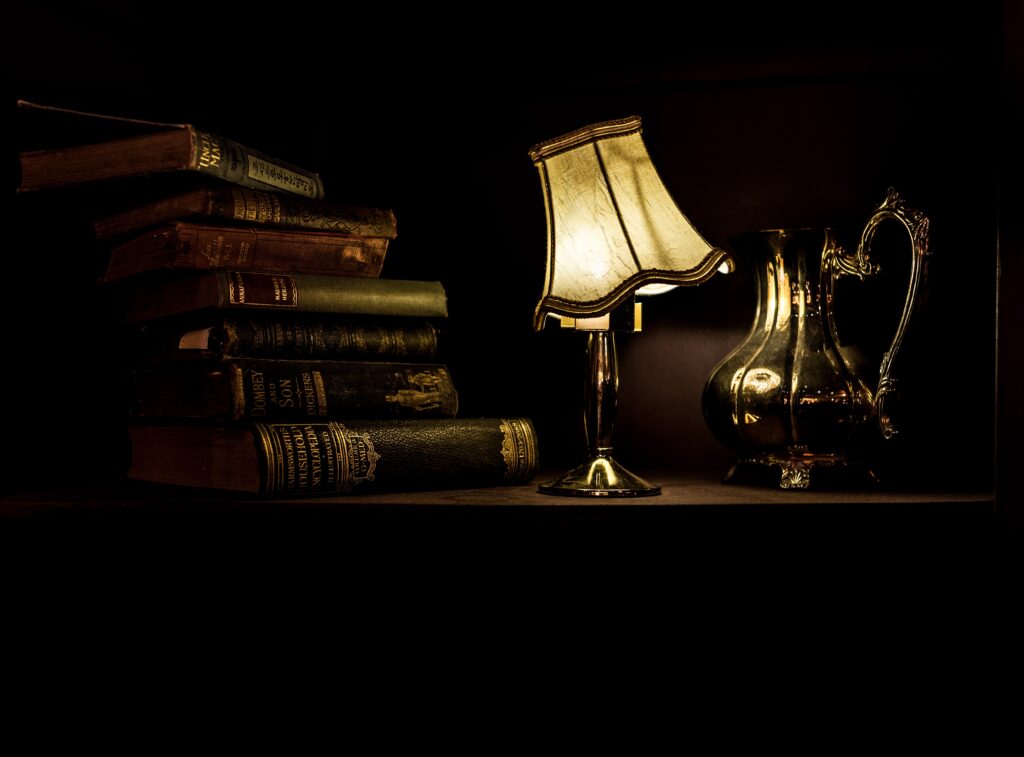
例えば夜寝る前に読書をする、といった場合「オーディオブック」と「電子書籍」が良いですね。
オーディオブックであれば、聴くだけなので、暗所でも安心して読書をすることができます。
電子書籍も画面が発光しているので、暗所でも読書は可能ですが、やはり目が疲れますよね。
⑧保存期間
保存期間は「オーディオブック」「電子書籍」が強いです。
一度購入した書籍はクラウド上に保存されるので、仮にデバイスを紛失したとしても再度ダウンロードすることができます。
一方、紙の本は水に濡れたり破れたり、紛失したらもうおしまいですよね。紙の劣化などもありますので、長期間の保存に適しているのはオーディオブックや電子書籍になります。
⑨読書量の確保

読書量を確保しやすいのは何と言っても「オーディオブック」です。圧倒的です。
オーディオブックは「聴くだけでOK」ですからね、忙しい社会人や主婦の方でも十分な読書量を確保することができます。
通勤/通学時間、家事の時間なども有効に活用することができますよ。
⑩バッテリー

バッテリーで言うと「紙の本」が最強です。
というかそもそも紙の本にはバッテリーという概念がありませんからね。
オーディオブックや電子書籍はデバイスの充電を気にする必要があります。
「読書したいのにスマホのバッテリーがなくてできない」なんて心配をしなくてよい分、紙の本は大きなアドバンテージですよね。
それぞれの使い分け方法は?
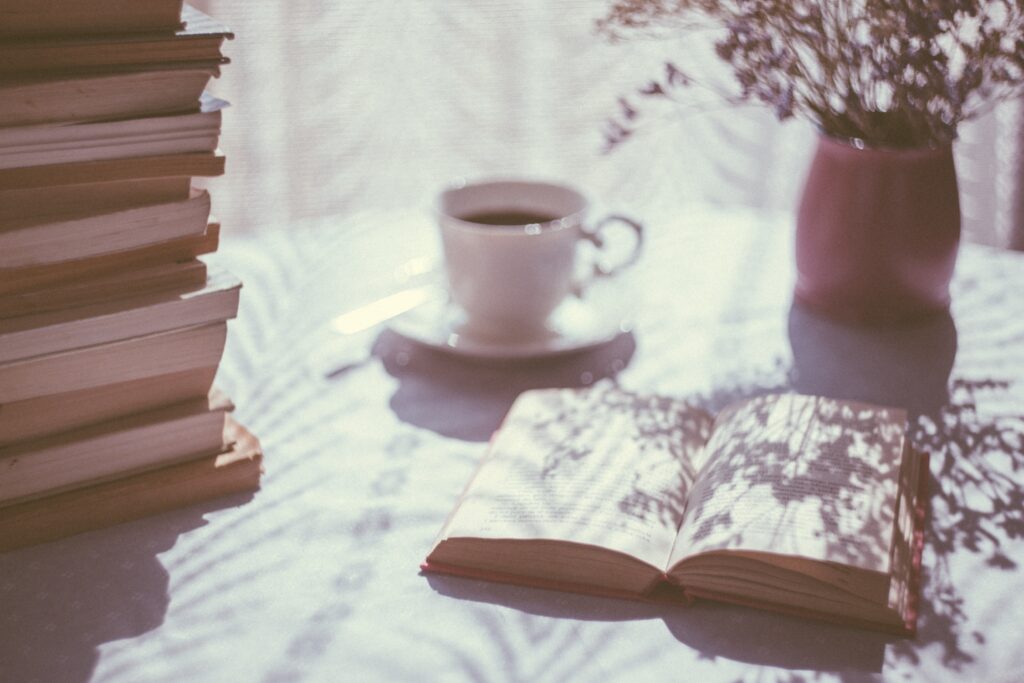
それぞれの使用場面、どのんな本が良いかをまとめていきたいと思います。
オーディオブック

●利用するタイミング:ながら時間、やる気が出ないとき、移動中
●読む本の種類:小説・ビジネス書・中味をざっくりと把握したい本
●おすすめの読み方:倍速で聴く
オーディオブックの特徴はなんといっても「聴いているだけでOK」ということです。
つまり、受動的に読書をすることができるので、お風呂に入りながら~、筋トレしながら~、家事をしながら~、やる気がないとき~に読書をするのに向いています。
ただ、どうしても音だけしかないので、内容が難し過ぎる本は理解するのが難しいので、「中身をざっくり理解すればよい」という本を聞くのがオススメです。
それと、等倍で聴くと遅いのでばいそくできくことがおすすめですよ。
今なら1ヶ月間無料で体験できるので興味がある方は是非お試しあれ。
▶Audible(オーディブル)▶Amazon Audible(オーディブル)とは?【オーディオブックの使い方・メリット・料金を初心者の方へ詳しく解説】
▶audiobook.jpを詳しくご紹介【特徴/プラン/メリット・デメリット/口コミ・評判/始め方・解約方法/注意点/おすすめ本】
電子書籍
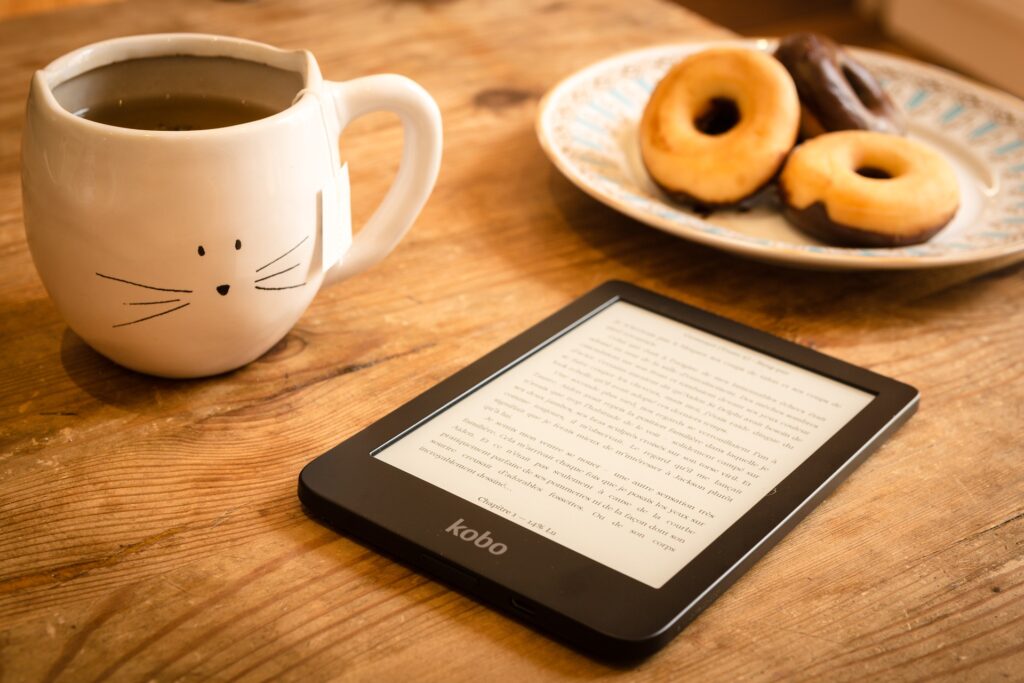
●利用するタイミング:通勤/通学時、数分間の空いた時間
●読む本の内容:図解がない本であれば何でもOK
●おすすめの読み方:気になった箇所にマーカーを引きながら読む
電子書籍はスマホさえあればいつでもどこでも読書ができるので、外出中の時間があるタイミングで読書をする際に利用しましょう。
読みながら気になった箇所にマーカーをすることで記憶に定着しやすくなりますよ。
「スマホで聴くとバッテリーが心配」という方はKindle専用の端末を利用すると良いですよ。
紙の本
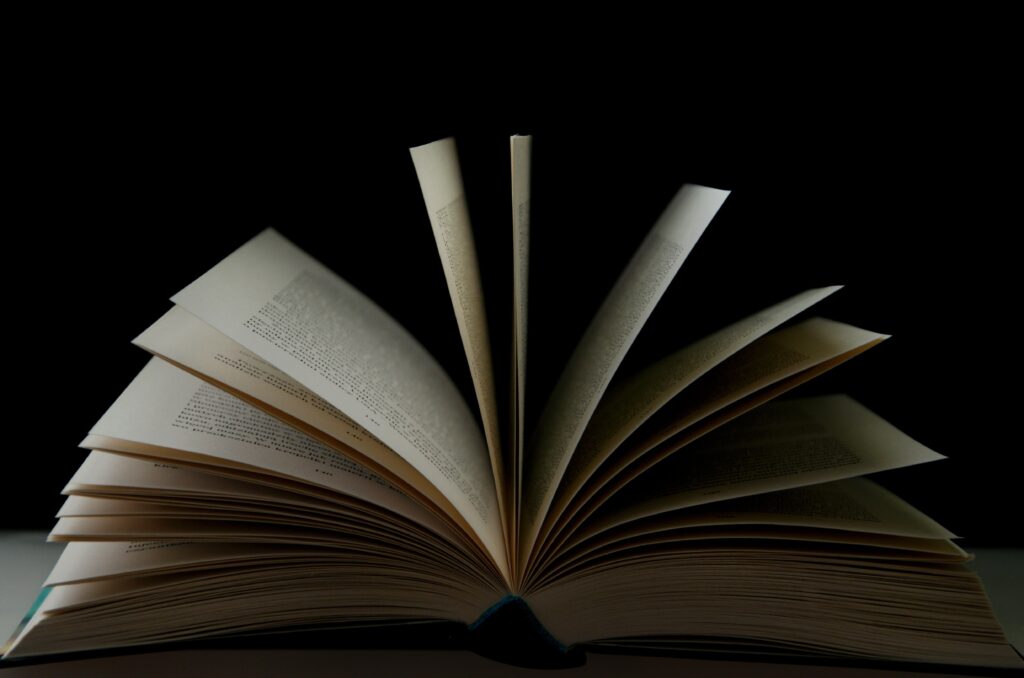
●利用するタイミング:自宅で時間がとれる時
●読む本の内容:何でもOK、内容を熟読したい本
●おすすめの読み方:気になった箇所に線を引いたり付箋を貼りながら。
紙の本はどうしても持ち運びが不便なので、家にいるとき、じっくりと読書できる時に利用するようにしましょう。
紙の質感を感じながらペラペラとページをめくっていくだけでとてもリラックスるすることもできます。
オーディオブックや電子書籍とは異なり、マーカーを引いたりできないので、マーカーを引いたり、付箋など貼りながら気になったことをメモしていくと記憶へ定着しやすくなるのでおすすめです。
まとめ
それぞれ特徴があるので、場面に応じて使い分けることが大切ですね。


